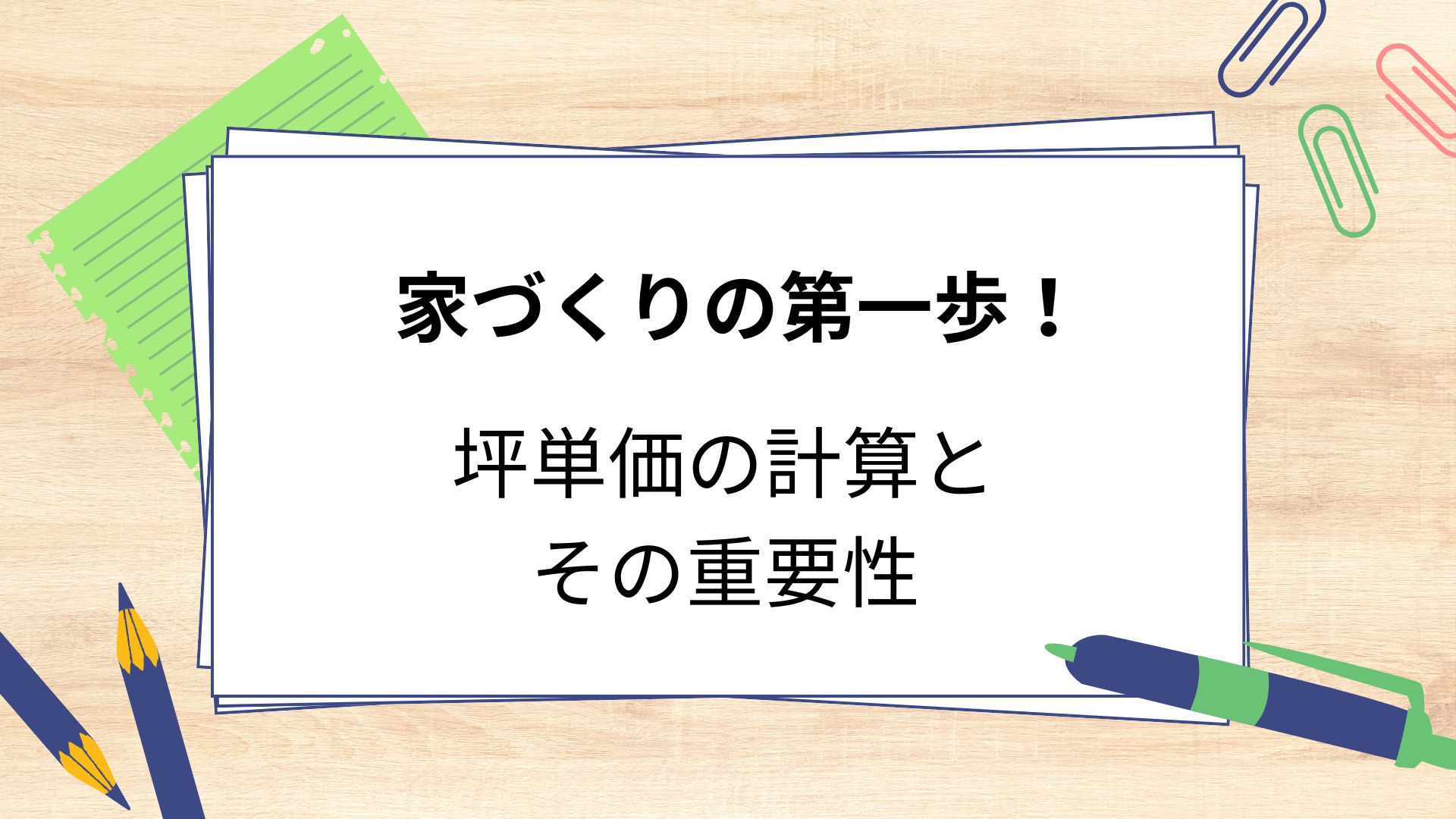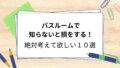こんにちはOFEです。
家づくりを考え始めたとき、「坪単価」という言葉が急に出てきて戸惑ったことはありませんか?「坪単価って何だろう?」と疑問に思う方も多いでしょう。なんとなく聞いたことはあるけど、詳しくはわからない。そもそも、「坪」って何?と感じる方も多いのではないでしょうか。
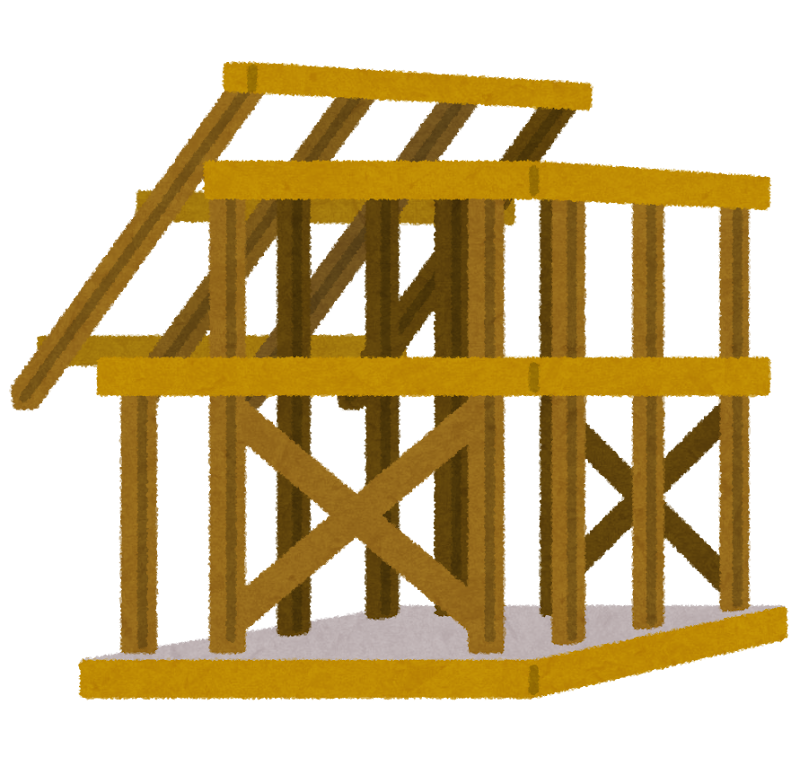
坪単価は、家づくりにおいて非常に重要な指標となります。そのため、坪単価をしっかりと理解し、どんどん活用していただきたいと思います。今回の記事では、皆さんが抱く坪単価に関する疑問を、どこよりもわかりやすく解説していきます。
本記事とを読むと次のことがわかります。
・坪単価を理解し、工務店やハウスメーカー選びが楽になります!
・家を建てる上で、予算の調整や賢い判断ができるようになります!
この記事を書いている私は、建材メーカーを経て、設計事務所に勤務し、建築士、インテリアコーディネーターとして住宅業界に20年間携わってきました。
自身の家づくりに関しては、10年間賃貸住宅に住み、7年間分譲マンションに住んだ後、その売却益を頭金にして注文住宅を建てました。その際、建築士でありながらハウスメーカーでの建築も検討し、モデルルームを訪れたり、複数の会社と打ち合わせを重ねました。最終的には工務店で建てることを選びましたが、ハウスメーカーについても詳しく知ることができ、様々な側面を理解することができました。この経験を活かし、「プロから見た家づくり」をお伝えしたいと考えています。
坪単価(つぼたんか)とは
坪単価(つぼたんか)とは、家を建てる際に住宅会社が建物のおおよその金額を一言で伝えるための単位です。
坪単価は非常に便利なものですが、知識が浅く、使い方を間違えると誤った判断をすることになってしまい、後悔する結果となることがあります。したがって、しっかり理解をした上で、使うことが重要です。
坪単価とはおおよその1坪(3.3㎡)あたりの建築費のことを指します。
「1坪?」「坪って、なんか中途半端な数字…」と感じるかもしれません。実際、家づくりを考え始めるまであまり耳にすることのない単位です。
坪単価の坪(つぼ)とは?
あまり耳にしたことの単位なので、まずは坪単価の「坪(つぼ)」という単位について解説します。
坪とは尺貫法という明治時代より使われている単位のひとつです。不動産に関して一般的には広く利用されていますが、実は契約上の書類では坪での表記は認められていません。それでもなお、現在も一般的に広く坪という単位が利用されているには理由がありますので、順に解説いきましょう。
1坪(ひとつぼ)=3.3㎡
このように「1坪」とは、3.3㎡という中途半端な広さを表します。なぜこんな中途半端な数字なのでしょうか?
実は、この一坪という単位は、畳2枚分の面積に相当します。畳を2枚並べると正方形になるため、その広さが3.3㎡となるのです。
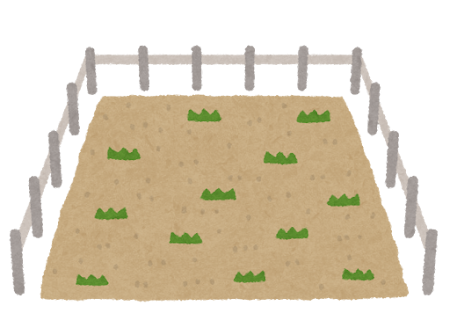
細かく計算してみると、
畳1枚分は、縦1.82m×横0.91m=1.65㎡
畳2枚分は、縦1.82m×横1.82m=3.3124㎡
このように、畳という単位からら坪という数字は生まれています。どうでしょうか。多くの人は「畳(じょう)」という単位には馴染みがあるかもしれません。皆さん、部屋を決める際に一度は間取図で「畳(じょう)」の表記を見たことがあるでしょう。そして自分の部屋は6畳(ろくじょう)とか、リビングは10畳(じょう)などと話をする際に実際に使っているかもしれません。このように部屋の広さを表す単位としては畳を使うことが多いですね。
㎡で書かれているよりも、6畳と書かれている方が広さのイメージしやすいのではないでしょうか?
また、広くなりすぎると畳の枚数だけではイメージがつかなくなるので、広さが大きくなる敷地などになると坪(つぼ)という単位がでてきます。60畳の土地といわれても、ちょっとイメージが湧きにくいですよね。それを30坪の土地と言うと、畳(じょう)と隣り合う単位としてより広い面積の土地も家も理解しやすくなります。
ちなみに60畳の土地は30坪×3.3=99㎡、または40坪×3.3=132㎡となります。
このようにして、互換性を持ちながら広さを表せるので、今もなお、日本では定着しているのだと思います。
坪単価とは
さて、本題に戻って、「坪単価」について解説します。
建物の本体価格÷延床面積
建物の本体価格を延べ床面積で割ると、坪単価が算出されます。
「え?本体価格を床面積で割るとはどういうことですか?」と混乱されるかもしれませんね。
延床面積とは
2階建ての場合、1階と2階の全てのフロアの面積の合計のことです。ただし、以下のような特定の部分は含まれないことがあります。詳細は下記※をご覧ください。
※延べ床面積:建物の全ての階における床面積の合計です。ただし、吹き抜け部分、天井高1.4m以下のロフトや外壁で囲われていないベランダ、バルコニー、玄関ポーチ、屋外階段などは含まれません。
坪単価の計算方法
本体価格÷延べ床面積(建物の床面積の合計)=坪単価
例)本体価格2600万円
1、2階の延べ床面積120㎡の家とすると
120㎡÷3.3≒36坪
2600÷36=坪単価72.2万円
このように計算すると、Aのハウスメーカーは坪単価72.2万円の家を作る家だと判断できます。
ここで、また疑問に思うのが本体価格ってなに?ということです。ハウスメーカーがだしてくる見積金額が本体価格なのかと疑問に思う人も多いでしょう。実は、坪単価にはデメリットやロジックがあり、ハウスメーカーや工務店ごとに項目が異なるため、見積金額=本体価格ということは危険です。
本体価格に含まれる工事を具体的に説明をすると、下記の項目の価格となります。
本体価格とは
- 仮設工事、
- 基礎工事
- 木工事
- 屋根、板金工事
- タイル工事
- 外壁工事
- 左官工事
- 建具工事
- 内装工事
- 塗装工事
- 設備工事
- 雑工事
ずらっと書いてしましましたが、逆に言えば、見積に含まれていても、本体価格から除外しなければならないものがあります。
それが付帯工事と諸経費です。
付帯工事とは、外構造園工事、冷房暖房エアコン工事、照明設備。工事、ガス管の敷き込みや浄化槽設置工事。
- 諸経費とは、工事とは異なる費用。登記費用・印紙代・ローン手数料・火災保険料・仮住まい費用
坪単価で計算してみよう
では実際に計算をしてみましょう。
坪単価90万円のハウスメーカーで120㎡の家を建てた場合の金額を計算する場合には、
120÷3.3=36.36坪
90万円×36.3坪=3267万円
よって、3267万円+付帯工事費+諸経費=全体総工費○○円と金額でてきます。
ちなみに付帯工事や諸経費は全体総費用の20%程度。本体工事費は全体総費用の80%程度といわれていますので、ざっくり計算すると全体総工費は4083万円くらいになるだろうと検討がつきます。

坪単価での比較
このように坪単価がわかると下記のような情報や判断材料を得ることができます。
- 予算の把握
家を建てる際の総費用を見積もるために利用できるようになります。予算内でどの程度の広さや仕様の家が建てられるかを具体的にイメージできます。 - コストパフォーマンス
複数のハウスメーカーや工務店を比較する際に坪単価という同じ条件で比較することでコストパフォーマンスを評価できます。坪単価が高い場合どのようなところで価格があがっているか、品質やサービスが優れているのか等判断材料になります。 - 建築プランの調整
坪単価をもとに建築プランや仕様を調整することでコストを抑えつつ理想の家の実現できます。 - 市場価格の理解
不動産市場の相場を理解できるようになります。
これにより適正価格での購入が可能になります。 - 資金計画
住宅ローンを組むとき、自己資金計画の場合に坪単価をもとにした具体的な資金計画を立てることができます。
工法による坪単価の違い
主な構造、工法による坪単価の違について解説していきます。
坪単価とは工法によってざっくりと金額の算出ができます。下記のように構造によってすでに金額が異なりますので、ハウスメーカーを決める際に、どのような構造で建てていくかを比較検討する際に利用できます。
- 木造 木造住宅の坪単価は約68.3万円
- 鉄骨造 鉄骨造住宅の坪単価は約97万円
- 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート住宅の坪単価は100.3万円
参考:2024年(令和6年)国税庁のホームページより地域別・構造別の工事費用表(1m当たり)【令和6年分用】|国税庁
坪単価の落とし穴
上記で既にお伝えしましたが、坪単価(つぼたんか)とは、家を建てる際に住宅会社が建物のおおよその金額を一言で伝えるための単位で、非常に便利なものです。しかし、失敗しないためには注意が必要です。
住宅会社ごとに見積もりの仕方が異なることがあり、それを知らずに坪単価のみで比較してしまうと、比較対象が異なるため、正しい比較ができません。
したがって、しっかり理解した上で使用することが重要です。坪単価○○円!!とうたっている住宅会社もありますが、算出方法がどうなっているか確認する必要があります。
また、見積もりされた工事項目が同じように見えても、設備のグレード(仕様)によって算出結果が異なるため、ハウスメーカーや工務店の比較をする際には、各社できるだけ同じグレードの状態で見積もりをお願いし、坪単価を計算することで比較することができます。
予算を見積もる場合には、坪単価以外にかかる費用も必ず含めてください。
坪単価のロジック
坪単価とは、一般的に床面積が大きいほど安くなります。床面積が大きくても、スペースが広くなるだけで、部屋の数や設備の数などが増えることがない場合があります。例えば、同じ4LDKという家ならば、面積が2倍になったとしても床材や屋根材が多少増えるだけで、設備の数が2倍になるわけではありません。
したがって、狭小住宅よりも床面積が大きいほど坪単価は安くなります。
坪単価を安くするするには
- シンプルにする
家の形状がシンプルであればあるほど、費用を抑えることができます。複雑な形状の工事は手間がかかるため、住宅工事費用が増加します。坪単価を押さえたい場合は、凹凸のない四角形にすることが効果的です。また、1階と2階が重なるような間取りにすることも重要です。屋根の形状も複雑にしないことがポイントです。 - 窓やドアを減らす
費用を抑えるためには、窓やドアを多く設置せず、シンプルにすることが重要です。
窓については、居室に対する法律上の制約があり、決まった大きさ以上の面積の窓をつけなければなりません。そのため窓を完全になくすことは不可能ですが、必要以上に多く設けると、建てた後のランニングコストも増えるため、必要最低限に抑えるとよいでしょう。
また、ドアについては、個室を多く設けることで壁やドアのコストが増加します。できるだけ安く済ませるためには、シンプルな間取りにすることが効果的です。
- 仕様のグレードを見直す
住まいの様々な材料は、安価なものから高価なものまでグレード幅が大きいです。
床材をはじめ、玄関ドアや浴室、トイレ、キッチン、壁紙に至るまで、価格帯に幅があります。一つ一つの単価についてはあまり目を向けていないかもしれませんが、良いものばかりを選んでいると、いつの間にか坪単価が大きくなっているかもしれません。ここはできるだけお金をかける、ここは思い切ってお金をかけない、といったこだわりを持つことで良いバラスンを取ることができます。
- 水回りをまとめる
坪単価を安くするためには、できるだけ水回りをまとめることが効果的です。
水回りを分散させると、配管設備の長さが長くなります。また、ガス管についても同じことが言えます。よって浴室、トイレ、キッチンはできるだけ、近くにまとめることで配管が短くて済み、安く建てることができます。
- 部屋ごとにグレードを考える
設備の仕様、グレードについても同様ですが、部屋ごとにグレードを考えてると、コストパフォーマンスよく上手にまとまります。
例えば、みんなの集まるリビングにはコストをかけ、個室はシンプルにしてあまりお金をかけないなど、部屋ごとにグレードを変えて考えていくことも大切です。
- 和室をつくらない
和室は実は洋室よりもお金がかかる部屋です。
和室の代表である畳やふすまは、初期費用だけでなくメンテナンスも必要です。また、床の間などを作る場合には、使われる柱や床材、天井材などのコストもあがります。
まとめ
以上、坪単価について理解できましたでしょうか。坪単価のポイントを押さえることで、効率的に家を建てることができます。しかし、コスト削減ばかりを考えると、生活がしにくくなったり、おしゃれさが失われたりする可能性があります。
坪単価を計算することで、家づくりの指標となることは間違いありません。坪単価という指標をしっかり理解し、比較検討や予算を考える際に活用しましょう。ただし、坪単価から算出された金額以外にも、付帯工事費や諸経費などの別途費用がかかることを忘れないでください。